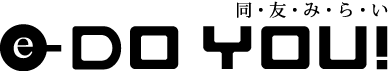奇跡のまち 別府百年ものがたり:第11回 明治のインバウンド客を迎えた幻のホテル/別府ホテル
今回掲載したのは、ハイカラな木造2階建てのホテルの絵葉書です。
その名も「別府ホテル」。
現在の明豊中学高校の位置に、明治44年(1911)9月11日に開業しました。
別府の歴史を振り返ると、この明治終わり頃は急速な発展の時期です。別府駅が開業したり、阪神方面と結ぶ航路が充実してきたりして、お客さんが急増しました。
海と陸の交通機関整備により、日本人だけではなく、きっと外国人客も増えるに違いない。そのためには、ホテルが必要だと考えてオープンしたのだと思います。
実際には、この頃に別府を訪れた外国人客は、明治43年(1910)が70人、44年(1911)が210人。この数字を記した書物(大正3年『別府町史』)は、鉄道開通や別府ホテル開業の影響もあって、140人も増加したと分析していますが、現代の私たちから見ると、いやはや、何とも頼りない数字ですよね。
それはともかく、別府ホテルはせっかく開業したものの、おそらく数年しかもたなかったと思われます。
7年後の大正7年(1918)の新聞に、外国人観光客誘致の必要性を説いた記者の文章が掲載されています。その中で、年々外国人客が増えているにも関わらず、唯一の別府ホテルは久しく門を閉じて、クモの巣が張っている、と嘆いています。
ところが、大正8年(1919)に、別の人がこのホテルを再開しました。でも、やはり経営はうまくゆかず、長続きはしませんでした。数年後には、満鉄(南満州鉄道)の療養所に変わってしまいます。
そんな、2度目のホテルの時期の様子について、私は新聞記者時代に、思い出話を聞いたことがあります。
近所に住んでいた女性なのですが、幼い時、ホテルに遊びに行くととても可愛がってくれたそうです。
「立派なホテルだった。赤じゅうたんが敷き詰めてあって、子供心にも印象に残っている。テニスコートもあった。あまり人(宿泊客)は来ていないようだった」と話してくれました。
もう一つ、このホテルの美しい思い出を綴った文章があります。
大分市生まれの洋画家、佐藤敬(さとう・けい/1906〜1978)をご存じでしょうか。実は子供時代は別府で過ごし、北小学校を卒業しています。
自叙伝『遙かなる時間の抽象』に、
「今でもスイスあたりにありそうな、美しいハイカラな木造西洋館の「別府ホテル」があったのを覚えていますか。六、七十年前、この荒野にこんな美しいホテルがあったのを今でも不思議に思っています。そしていつの間にか姿を消しました。このホテルを前景に山々を見ますと、まことに異国的な美しい眺めでしたが、写生など出来る年頃ではありません。」
と書かれています。
立派なホテルだったのに、長続きできなかったのは、おそらく、交通の問題でしょう。現代ならば、たとえば別府駅から自動車であっという間の距離ですが、当時は人力車でえっちらおっちら、やっと到着、という感じだったのではないでしょうか。
ただし、高台からは、別府湾が一望できて、眺めはすばらしかったと思われます。
大正2年(1913)夏に滞在した、著名なジャーナリストの徳富蘇峰が旅行記にスケッチを掲載しています。
早朝、東向きのバルコニーの椅子に腰掛け、葉巻の煙をくゆらせながら、別府湾に上る朝日を見物する様子を、さらさらっと描いているのですが、何とも味わいのある絵で、お見せできないのが残念です。
最後に、ちょっと付け加えます。佐藤敬の文章に「この荒野に」という言葉があり、違和感を覚えた方もいらっしゃるでしょう。
実は、別府ホテルの絵葉書の一枚に、建設前の写真を使用したものがあります。
大きな岩の上に、関係者が数人、腰掛けている場面なのですが、周囲も大きな石ころがごろごろしていて、まさに荒野という雰囲気です。おそらく昔の火山活動によって出来た風景だと思いますが、開発前の山の手一帯はそんな場所だったわけです。
※メイン画像説明
明治44年(1911)、現在の明豊中学高校の位置にオープンした、外国人向けの宿泊施設「別府ホテル」
profile

おの・ひろし:1953年、別府生まれ。別府の絵葉書収集家、別府の歴史愛好家。今日新聞記者時代に「懐かしの別府ものがたり」を長期連載。現在も公民館で講演するなど活動中。